【要約】(新装版)幸せがずっと続く12の行動習慣
幸福度を高める実証研究がまとめられた本
ポジティブ心理学の初心者向けに、幸福度の研究で有名なソニア・リュボミアスキー博士の最初の本、「幸せがずっと続く12の行動習慣」を紹介します。
この本は2012年ごろに出版されましたが、最近(2024年)になって新装版が出されました。内容は同じです。10年以上前に海外で話題になった本ですが、国内でも「ウェルビーイング」に関心が高まったことから、再注目される機会となりました。
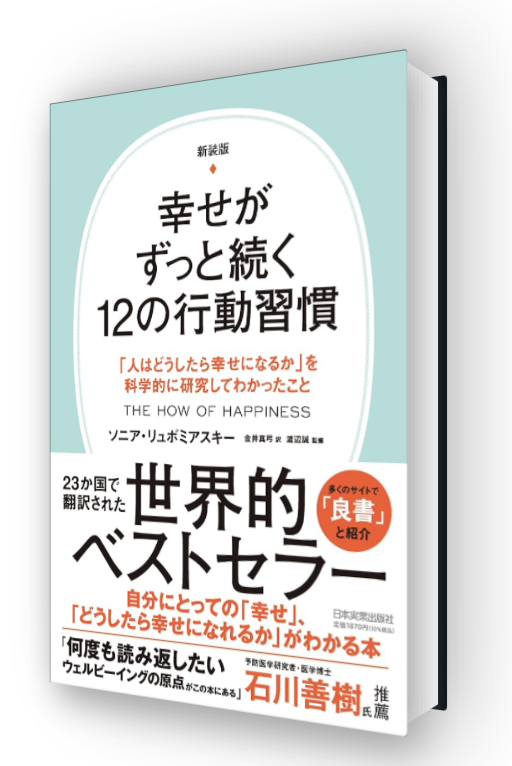
著者について
ソニア博士はポジティブ心理学の第二世代の研究者の一人で、リサーチを重視し、多くの賞を受賞し、メディアにも出演しています。博士のウェブサイトには、彼女の関わった論文のリストがあり、PDF形式でダウンロードできます。
博士は「リュボミアスキー教授の人生を「幸せ」に変える10の科学的な方法」という二冊目の本も執筆しています。
なお、博士は、(同じくポジティブ心理学の第二世代である)イローナ・ボニウェル博士と同じロシア系です。
幸福度における「40:50:10」とは?
コントロール可能な40%に焦点を当てる
この研究について話すと、私のスクールの受講生の反応は二つに分かれます。一部は遺伝であることにがっかりし、他は自分で影響を及ぼすことができる40%の部分に焦点を当てて前向きに考えます。
本書のテーマは、40%の領域に焦点を当て、幸せを続けるための12の行動について実証ベースの研究をまとめたものです。
その中でも、私のお気に入りは「不幸で居続けないために手に入れるべき習慣」についてです。その中で、ストレスや悩み、トラウマにどう対処するかが述べられています
私自身、ポジティブ心理学を学習していますが、つらいことがあると、頭ではわかっていても幸福度に良いことを実践することが「面倒だな、しんどいな」と思うことがあります。
そんなときは、無理にモチベーションを高めるのではなく、本書で紹介されているようなマイルドな回復法を行い、家族や友人などと対話して、おいしいものを食べてゆっくり眠るほうが、私には合っていると感じます。
マインドフルネスと幸福度
本書では、最後の章でマインドフルネスが幸せになる行動の一つとして紹介されています。瞑想を行っている私自身としては、瞑想には効果があると思います。
幸福度に関する実証研究に興味がある方は、ぜひ本書を読んでみてください。友人は本書をベースにした読書会を行っていますが、仲間と一緒に読むのにも適した本です。
心に残った言葉
「なぜでしょうか? 「幸せ」を科学的に研究するのは重要なことだと、強く考えているらかです。広大な大陸を横切ってざまざまな文化に接しみてると、世界の大半の人は々「幸せになこるとが人生で最も大切な目的だと、はっきりいっています。」
「幸せになろうとする人は、気分がさらよくなるばかりか、エネルギーが上 昇し、よりクリエイティブになり、免疫系が活発になり、人間関係が向上し、仕事の生産性が高まり、長生きさえできることが研究からわかっています」
「「裕福か、貧乏か」「健康か、病気がちか」「器量がいいか、人並みか」「既婚者か、離婚経験者か」などの生活環境や状況による違いは、幸福度のわずか10%程度しか占めない」
「おすすめしたい大切なポイントは、 幸せになたるめの方法はやりすなぎいようにして、ときどき変え、たえず新鮮なものにしておくことです。これは私の研究からわかったことで、変化に富んでいることはとても大事だからです」
「考えすぎると、悲しみは消えないどころかひどくなる場合もあり、偏ったネガティブな考えが育ち、問題を解決する能力が損なわれ、意欲が低下し、集中力や自発性が妨げられるのです」
「人と人との絆の最も重要なポイントの1つは、「ストレスにさらされ、苦 悩し、トラウマに悩まされたときに、まわりの人からの支援が得られること」です」
「うまくいく結婚生活の秘訣とは何でしょうか。 その1つは、「夫婦がたくさん話すこと」です。うまくいっている夫婦は、うまくいかない夫婦に比べて、一緒にいて話す時間が週に5時間は多いとの研究結果が出ています」
「では、乳ガンの患者が得た「思恵」といはったい何なのでしょうか? ガンと診断された女性たちは、自分にとって大切なものを見直し、人生でほんとうに重要なものを考える必要に迫られました。最も多かったのは、「仕事よりも家族を大事にすること」でした。そして自分にとって一番大切な人間関係にもっと時間をかけ、家事などに費やす時間を減らそうと決めたのです」
「驚いたことに、ほほ笑みかけたり、何かに没頭したり、活力や熱意があるふりをするなど、幸せであるかのように振る舞うと、幸福の恩恵を手にするだけでなく、実際により幸せになれるのです」
目次
1 幸せがずっと続くためにすべきこと
・自分で変えられる40%に集中しよう
・幸福度の測り方
・幸せになるための最適な行動の選び方
2 幸福度を高める12の行動習慣
・感謝の気持ちを表わす
・楽観的になる
・考えすぎない、他人と比較しない
・目標達成に全力を尽くす
・内面的なものを大切にする
・身体を大切にする―瞑想と運動
3 40%の行動習慣が続く5つのコツ
・ポジティブな感情をより多く体験する
・タイミングをはかり、行動に変化を起こす
・社会的なつながりを大切にする
・意欲と献身的な努力をもって人と関わる
・行動は繰りかえすことで習慣になる
執筆者の紹介
久世浩司
認定レジリエンス マスタートレーナー
応用ポジティブ心理学準修士(GDAPP)
慶應義塾大学卒業後、P&Gに入社、社会人向けのスクールを設立。レジリエンス研修の普及と講師の育成に取り組む。NHK「クローズアップ現代」などでも取り上げられ、著書による発行部数は20万部以上。研修・講演会の登壇は上場企業から自治体・病院まで100社以上の実績がある。
主な著書
『「レジリエンス」の鍛え方』
『なぜ、一流の人はハードワークでも心が疲れないのか?』
『なぜ、一流になる人は「根拠なき自信」を持っているのか?』
『リーダーのための「レジリエンス」入門』
『なぜ、一流の人は不安でも強気でいられるのか?』
『親子で育てる折れない心』
『仕事で成長する人は、なぜ不安を転機に変えられるのか?』
『マンガでやさしくわかるレジリエンス』
『図解 なぜ超一流の人は打たれ強いのか?』
『成功する人だけがもつ「一流のレジリエンス」』
『眠れる才能を引き出す技術』
『一流の人なら身につけているメンタルの磨き方』
『「チーム」で働く人の教科書』
